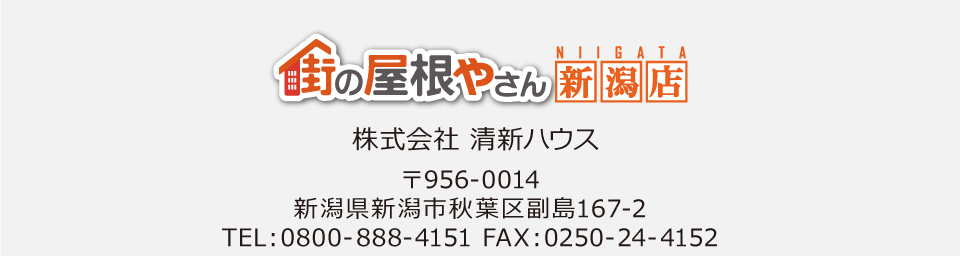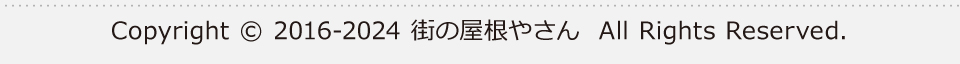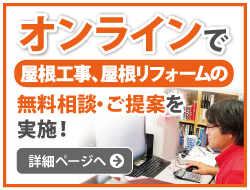

今回の雨漏れ箇所は廊下の天井部分でした。
雨の日には「ポタポタ」と音を立てて水が落ち、床が濡れてしまうため、桶を置いて対処されていたそうです。
天井を見上げると、黒ずんだシミが広がり、触ると湿っている状態でした。
このまま放置すると、天井材や内部の木材が腐食してしまい、カビの発生や構造への影響も出てくる恐れがあります。

屋根の上を確認すると、下地部分(木材)が雨水を吸い込んで黒く変色していました。
長年、雨水が染み続けていたようで、木材の小口がボソボソになっており、手で触ると剥がれ落ちそうな状態。
このような場合、下地の補強工事を行わなければ再発する可能性が高くなるため、放置すると屋根全体の耐久性が低下し、最終的には大規模な修繕が必要になることもあります。

さらに詳しく調査したところ、雨漏れの直上部分にある「土居部分」に原因がありました。
「土居串」とは、屋根の端や壁際など、瓦を固定するための木材部分のことで、この部分の瓦に細かな隙間が生じており、そこから強風に乗った雨が吹き込んでいたと考えられます。
瓦屋根は“上から下へ雨を流す構造”ですが、横風や台風の際に吹き込みがあると、こうした部分から雨水が内部へ侵入することがあります。

今回は、土居串部分の瓦をやり替える工事をご提案しました。
まず、隙間ができている瓦を丁寧に取り外し、内部の下地を補強。
その後、新しい防水シート(ルーフィングシート)を施工し、既存瓦を再利用して復旧しました。
瓦をすべて交換する全面リフォームではなく、必要な部分のみを修繕するため、費用を抑えながら効果的に雨漏れを防ぐことができます。
また今回のように、見た目では瓦がきれいに見えても、内部の下地や防水層が劣化していることは多くあります。
特に新潟市のような雪・雨・風が強い地域では、屋根への負担が大きいため、早めの点検が大切です。
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん新潟店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2025 街の屋根やさん All Rights Reserved.